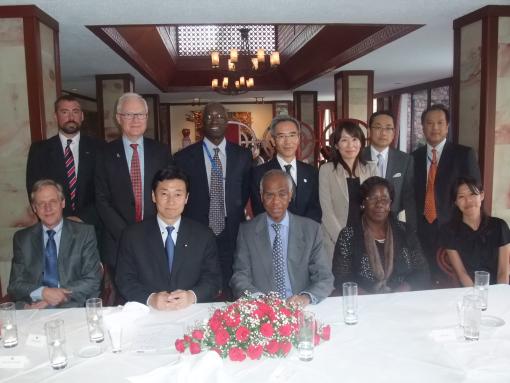BLOG
中央アジア・コーカサス・中東・アフリカ出張(その⑥:「ケニア編」)
1.アメリカ留学中の1992年に訪問して以来、17年ぶりのケニアである。あの時は、バックパックをかついで安い宿に泊まり、乗合バスで「マサイマラ」や野生動物の生息する国立公園を訪れた。今では考えられないような危険性をはらんだ旅で、“若さ”ゆえの行動か、と今ではハラハラした気持ちになる。その時は、キリンやシマウマを初めて見つけた時には「バシバシ」写真を撮っていたが、やがてキリンやシマウマは山ほどいることが分かり、すぐに飽きて、やはりゾウ、ライオン、サイ、カバ、チータ、…こうした野生動物は中々出会えず、目を凝らして探したのをよく覚えている。
2.ケニアの首都ナイロビは、17年前と同じ建物があり(写真①)、懐かしく思い出すが、近代化が進んだ()一方で、失業者は多く(現在、失業率は約40%:)、渋滞の中で車が止まれば、すかさずいろんな物を売りに来る。非常時用の三角を売りに来た国は初めてだ()。しかし、「物乞い」ではなく「売る」姿勢は大事だ。ノーベル平和賞受賞のユヌス教授のグラミン銀行による「マイクロ・クレジット」にもつながるものであり、貧困から自立する第一歩である。
3.ケニア・ナイロビでは、もう一人のノーベル平和賞受賞者のマータイ女史にお会いした()。マータイ女史は、「もったいない運動」はじめ環境保全運動のリーダーであり、この度、日本政府より旭日大綬章の叙勲を受賞されることとなり、そのことを伝達した次第であるが、コンゴ川の流域の森林保全などについて意見交換を行った。私は、1995年に日本で最初の「リサイクル法」の条文を書き上げた一人であり、例の三角形の「リサイクルマーク」をペットボトルなどに表示を義務付けたため、マータイ女史との面談は感慨もひとしおであった。マータイさんからは、三脚のイス(物置き)をプレゼントされた。三本の脚は三R(「リサイクル」「リユース」「リデュース」)の象徴しているとのこと、しかも、風呂敷に包んで渡された。もちろん、梱包紙の節約であり、風呂敷は、マータイさんがまた別の所で使うのである。大変楽しい会談であった。
4.ケニアのウェタングラ外務大臣とも意見交換()。ケニアは東アフリカの玄関として、モンバサ港の拡張計画などを日本の経済援助により実施することとなっている。国際会議での協力を含めて、様々な意見交換を行った。
5.その後、日本も資金援助しているケニアのPKO訓練センターを視察。キボチ司令官のご案内のもと()、施設を視察。この地で今後、停戦監視や選挙監視などのPKO活動(平和維持活動:5月24日活動報告参照)を行う兵士や警察官、文民の訓練を行うのである。
ケニアのみならず、東アフリカの国々から幅広く人材を募り、日本からも専門家を派遣し、研修・訓練を行う。この分野では日本はもっと貢献できると確信している。そんな思いを持ち、また、世界の平和を祈りつつ、植樹を行った()。何年か後に、また訪れたくなるだろう。
6.また、ケニアは、海賊問題の背景ともなっているソマリア問題に対処するための国際機関の拠点だ。アブドラ・ソマリア国連事務総長特使、オフィア・UNHCRケニア代表、オルセン・UNICEFソマリア代表、グーセン・WFPソマリア事務所長、そして旧知の瀬谷ルミ子・NPO法人・日本紛争予防センター事務局長とソマリア情勢について意見交換を行った()。全体としては、周辺国を含めて、安定化にはしばらく時間がかかるとの見通しであったが、先般の一定の停戦合意を成立させた暫定政府TFGは未だ基盤が脆弱であるが、それ故に国際社会はシェイク・シャリフ大統領を支援すべきであると強調された。また、日本の36億円の支援に大変な謝意を示された。WFPやUNICEFに加えて、瀬谷ルミ子さんのNGOなどもソマリア難民や国内避難民(IDP)の支援にソマリア国内に入っての活動を開始・強化すべく検討を進めているとのことであった。危険を伴う仕事であり、その献身的な姿勢に心から敬意を表すとともに、日本にもこうした平和構築の分野で少しずつ人材が生まれ、そして、経験やノウハウが蓄積されてきていることを本当に嬉しく思う。私自身さらに力をいれたいと思う。
7.また、昨年の横浜でのTICADⅣ(第4回アフリカ開発会議:2008年5月30日ブログ参照)において、小泉純一郎元総理が提唱しスタートした「野口英世賞」の初代受賞者であるウェレ博士ともお会いした()。ウェレ女史は、女性の活動を支援され、衛生分野でも膨大な貢献をされている。引き続き支援を行っていきたい。
8.そして、何より嬉しかったのは、このケニアでも48人もの海外青年協力隊の若者が、ケニアの田舎の学校や病院で、献身的な活動をしているとのことだ。週に1度しか水が出ず、電気もないような場所で、子どもたちに算数を教えたり、母子の健康維持のための活動などを行っているのである。世界の途上国のへき地で2000人を超える日本の若者が、このような活動を行っていることは本当に誇りに思う。こうした活動こそが日本の進むべき道であり、また、こうした経験を通じて優れた人材が育っていくのである。是非しっかり応援したい。
今回も、地元の兵庫の神戸市西区(明石のすぐ隣)の青年が、貧しい子どものための心のケアや職業訓練を行っていた(の右から2人目。背の高い若者)。古タイヤからサンダルを作ったりするのを教えているのであるが、迷わずお土産に多くのサンダルを買って帰った。明石や淡路の私の事務所では、このサンダルを使っている。是非一目見にお立ち寄りください。
2.ケニアの首都ナイロビは、17年前と同じ建物があり(写真①)、懐かしく思い出すが、近代化が進んだ()一方で、失業者は多く(現在、失業率は約40%:)、渋滞の中で車が止まれば、すかさずいろんな物を売りに来る。非常時用の三角を売りに来た国は初めてだ()。しかし、「物乞い」ではなく「売る」姿勢は大事だ。ノーベル平和賞受賞のユヌス教授のグラミン銀行による「マイクロ・クレジット」にもつながるものであり、貧困から自立する第一歩である。
3.ケニア・ナイロビでは、もう一人のノーベル平和賞受賞者のマータイ女史にお会いした()。マータイ女史は、「もったいない運動」はじめ環境保全運動のリーダーであり、この度、日本政府より旭日大綬章の叙勲を受賞されることとなり、そのことを伝達した次第であるが、コンゴ川の流域の森林保全などについて意見交換を行った。私は、1995年に日本で最初の「リサイクル法」の条文を書き上げた一人であり、例の三角形の「リサイクルマーク」をペットボトルなどに表示を義務付けたため、マータイ女史との面談は感慨もひとしおであった。マータイさんからは、三脚のイス(物置き)をプレゼントされた。三本の脚は三R(「リサイクル」「リユース」「リデュース」)の象徴しているとのこと、しかも、風呂敷に包んで渡された。もちろん、梱包紙の節約であり、風呂敷は、マータイさんがまた別の所で使うのである。大変楽しい会談であった。
4.ケニアのウェタングラ外務大臣とも意見交換()。ケニアは東アフリカの玄関として、モンバサ港の拡張計画などを日本の経済援助により実施することとなっている。国際会議での協力を含めて、様々な意見交換を行った。
5.その後、日本も資金援助しているケニアのPKO訓練センターを視察。キボチ司令官のご案内のもと()、施設を視察。この地で今後、停戦監視や選挙監視などのPKO活動(平和維持活動:5月24日活動報告参照)を行う兵士や警察官、文民の訓練を行うのである。
ケニアのみならず、東アフリカの国々から幅広く人材を募り、日本からも専門家を派遣し、研修・訓練を行う。この分野では日本はもっと貢献できると確信している。そんな思いを持ち、また、世界の平和を祈りつつ、植樹を行った()。何年か後に、また訪れたくなるだろう。
6.また、ケニアは、海賊問題の背景ともなっているソマリア問題に対処するための国際機関の拠点だ。アブドラ・ソマリア国連事務総長特使、オフィア・UNHCRケニア代表、オルセン・UNICEFソマリア代表、グーセン・WFPソマリア事務所長、そして旧知の瀬谷ルミ子・NPO法人・日本紛争予防センター事務局長とソマリア情勢について意見交換を行った()。全体としては、周辺国を含めて、安定化にはしばらく時間がかかるとの見通しであったが、先般の一定の停戦合意を成立させた暫定政府TFGは未だ基盤が脆弱であるが、それ故に国際社会はシェイク・シャリフ大統領を支援すべきであると強調された。また、日本の36億円の支援に大変な謝意を示された。WFPやUNICEFに加えて、瀬谷ルミ子さんのNGOなどもソマリア難民や国内避難民(IDP)の支援にソマリア国内に入っての活動を開始・強化すべく検討を進めているとのことであった。危険を伴う仕事であり、その献身的な姿勢に心から敬意を表すとともに、日本にもこうした平和構築の分野で少しずつ人材が生まれ、そして、経験やノウハウが蓄積されてきていることを本当に嬉しく思う。私自身さらに力をいれたいと思う。
7.また、昨年の横浜でのTICADⅣ(第4回アフリカ開発会議:2008年5月30日ブログ参照)において、小泉純一郎元総理が提唱しスタートした「野口英世賞」の初代受賞者であるウェレ博士ともお会いした()。ウェレ女史は、女性の活動を支援され、衛生分野でも膨大な貢献をされている。引き続き支援を行っていきたい。
8.そして、何より嬉しかったのは、このケニアでも48人もの海外青年協力隊の若者が、ケニアの田舎の学校や病院で、献身的な活動をしているとのことだ。週に1度しか水が出ず、電気もないような場所で、子どもたちに算数を教えたり、母子の健康維持のための活動などを行っているのである。世界の途上国のへき地で2000人を超える日本の若者が、このような活動を行っていることは本当に誇りに思う。こうした活動こそが日本の進むべき道であり、また、こうした経験を通じて優れた人材が育っていくのである。是非しっかり応援したい。
今回も、地元の兵庫の神戸市西区(明石のすぐ隣)の青年が、貧しい子どものための心のケアや職業訓練を行っていた(の右から2人目。背の高い若者)。古タイヤからサンダルを作ったりするのを教えているのであるが、迷わずお土産に多くのサンダルを買って帰った。明石や淡路の私の事務所では、このサンダルを使っている。是非一目見にお立ち寄りください。